セミリタイヤ、バリスタファイヤーに憧れている、独身50代の案山子です。今回のテーマは、「最大月7千円減!厚生年金への影響は?基礎年金改革の最新議論!」でっ!行きたいと思います👍
最近何やら、年金の仕組みについての変更がささやかれています。内容はとしては、政府は基礎年金を増やすために厚生年金の積立金を活用する案を検討しています。
検討理由として、就職氷河期世代など低年金に陥りやすい層を支援する目的で基礎年金を底上げする一方で、厚生年金加入者が不利益を被らないようにするための措置を盛り込む方向で進められています。
この改革案では、標準的な世帯では2040年度までに厚生年金の受給額が「月7千円減る」見込みがあるとされています。これは、基礎年金の底上げのために厚生年金の積立金を活用する影響によるものです。この点については、厚生年金加入者の間で不公平感が広がる懸念もあります🤔
ただし、この案では一時的に厚生年金の受給額が減る可能性があるため、最終的に受け取る総額が減らないように調整する仕組みを考えています。
基礎年金だけを掛けている自営業者には良い話に聞こえるんですけど🙄
自営業者にとっては、良い話と捉えられる可能性が高いと考えます。基礎年金は全ての国民が受け取る制度なので、自営業者も恩恵を受けられます。
特に、今回の底上げ案が実現すれば、就職氷河期世代や低年金に陥りやすい層への支援として、自営業者を含む対象者にとってより安定した生活基盤を提供する一助になるかもしれません。
一方で、厚生年金加入者からは、自分たちの積立金が活用されることで公平性への懸念が出る可能性もあります。このバランスをどう取るかが重要な課題ですね。
案山子の様に厚生年金を掛けている就職氷河期世代もいるんだけど❓
案山子のように、厚生年金をずっと支払ってきた就職氷河期世代にとって、この改正が不公平に感じてしまいます。年金制度は公平性と持続可能性を両立させる必要がある重要なテーマです。
第二次ベビーブーム世代の年金支払いに、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の積立金を活用しても、厚生年金加入者が負担に対して適切な受益を受けられないという不満が出るのは避けられないかもしれません。
現行の議論では「最終的な総額が減らないように調整する措置を設ける」という方向性で進められているようですが、それでも一時的な減少や具体的な仕組みの透明性が問われるでしょう。
特にボクたちの様な就職氷河期世代は、既に不安定な経済環境に直面してきた人たちです。負担増加や将来的な不確実性がさらに深刻に感じます😰
基礎年金を段階的に65歳まで積み立てる案もあったような❓
基礎年金と厚生年金の積立期間を同じ65歳にする議論が行われています。全体の公平性を保つ方法としては合理的に思えますが、案山子のように無職になった場合、60歳から65歳までの間に基礎年金の穴埋めができなくなる可能性があり、不安を感じます。
そのため、案山子が年金を受け取るまではルールを変更しないでほしいと願っています😅
一方で、この議論が進展していない背景には、現行制度の運用上の課題や、多様な所得層や就労形態への配慮があるのかもしれません。
基礎年金はすべての国民が対象のため、積立期間を厚生年金と揃えることで財源確保や公平性の新たな問題が生じる可能性も考えられます。
また、厚生年金加入者と基礎年金のみを積み立てている方々への影響を慎重に調整しているのかもしれません😀
全ての年金を厚生年金に一本化して労働者間の差をなくすて可能❓
ここからは、案山子の妄想ですが、厚生年金への一本化というアイデアは、労働者間の差を減らし、より公平な制度を目指す観点から考えました🧐
現在の年金制度は、基礎年金が全ての国民に適用され、厚生年金が会社員や公務員を中心に運用されています。そのため、自営業者やフリーランスの方々など、厚生年金に加入できない層との間で待遇に差が生まれることがあります。
一本化することでこうした不平等を解消し、誰もが等しく恩恵を受けられる制度設計が可能になります。ただし、そのためには以下のような課題を乗り越える必要があります。
社会的合意:多様な雇用形態や所得層を持つ国民が納得し、支持できる制度設計。
財源の統合:厚生年金と基礎年金の積立金をどのように調整するか。
制度移行:現在の加入者への影響を最小化しながら、新しい制度への移行をスムーズに進めるための仕組み。
これらの課題を考えると、先送りが好きな日本人には難しい内容なのかも知れませんね🤭
おしまい 😀
今回は、「厚生年金受給額が2040年度まで最大月7千円減ってしまうかも?」について思う所を書かせてもらいました。年金制度の改正議論は、多様な立場や環境にいる人々の声を反映しながら進める必要があります😄
基礎年金と厚生年金の積立期間を65歳まで統一する案には、全体の公平性を高める狙いがある一方で、無職や非正規雇用者が負担を抱えるリスクや、就職氷河期世代のような既に不安定な経済環境に直面している世代への影響も懸念されます。
そのため、任意加入制度の拡充や財源確保の仕組み、就労形態に応じた柔軟な対策が不可欠です。公正で持続可能な年金制度を築くためには、制度設計の透明性を高め、広く理解と納得を得られる議論が求められますね。
では!! バイバイ(^。^)y-.。o○
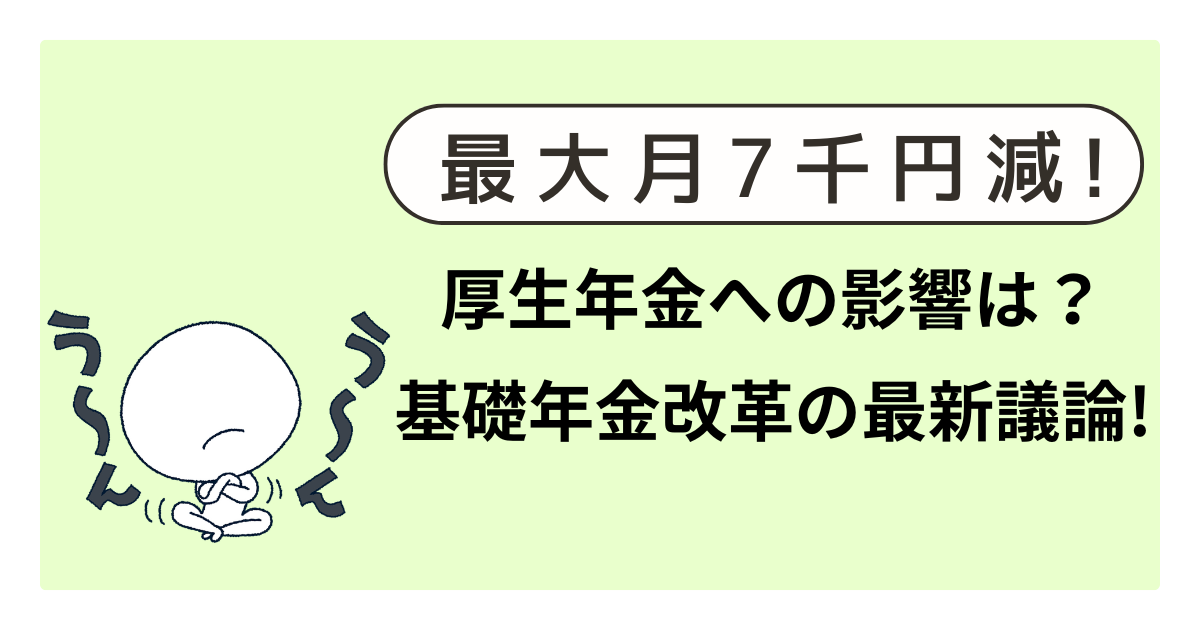


コメント